森林の「緑のダム」機能の科学的評価
森林は,洪水や渇水を緩和する機能を持つと考えられており,「緑のダム」と呼ばれることがあります。この機能を直接発揮しているのは,森の木ではなく,森の地面に層となってたまっている「森林土壌」です。森林土壌は透水性が大きいため,降った雨のほとんど全てを浸透させます。浸透した水の一部は一時的に土壌中に蓄えられ,遅れて流出します。このため,洪水時の流量が減少し,降雨後にも河川の流量が長期間維持されることになります。このような「緑のダム」の機能を,科学的に解明する研究を行っています。

滋賀県南部田上山地の天然林。不動寺の境内の森として,長期間人手が入っていません。

上の写真の天然林で掘削した土壌断面。表層は厚い落ち葉の層で覆われ,土壌中には層位区分(A,B,C層)が見られます。最下層には,基岩(花崗岩)が見られます。
このような断面の各層から土壌サンプルを採取して透水性(雨を浸透させる能力)や保水性(浸透した水を保持する能力)を計測し,土壌の発達過程や地形・地質・樹種による違いを調べています。
神戸六甲山のアラカシ林で,森林土壌を,構造をできるだけ乱さないように気を付けてサンプリングしました。さらに,同じ場所・深度で採取した土壌を円筒形容器にハンマーで突き固めて充填しました。それぞれのサンプルについて,間隙量と透水性を計測した結果が次のグラフです。
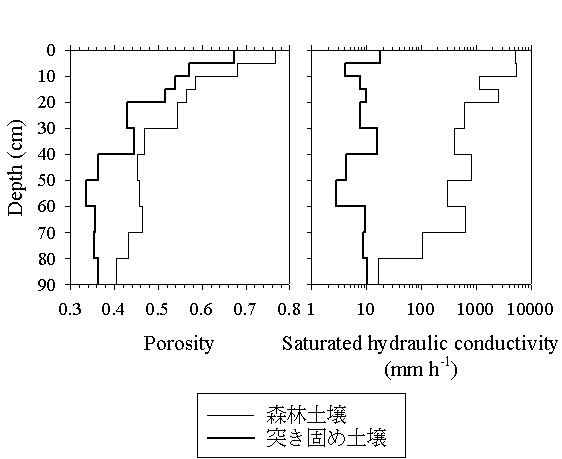
突き固めにより森林土壌の構造を破壊することによって,間隙率が2〜12%減少したことがわかります。森林土壌の飽和透水係数は,深さ80〜90cmを除いて100mm h-1以上であり,かなりの豪雨でも表面流は発生しません。一方,突き固め土壌の飽和透水係数は3〜20mm h-1と小さいため,表面流が頻繁に発生することになります。
森林土壌は,降雨波形をより緩やかな浸透波形に変換して下層に伝える「バッファー」の役割を果たしていると考えられます。この役割をより詳細に調べるために,土壌サンプルによる実験に加え,数値シミュレーションによる解析を行っています。
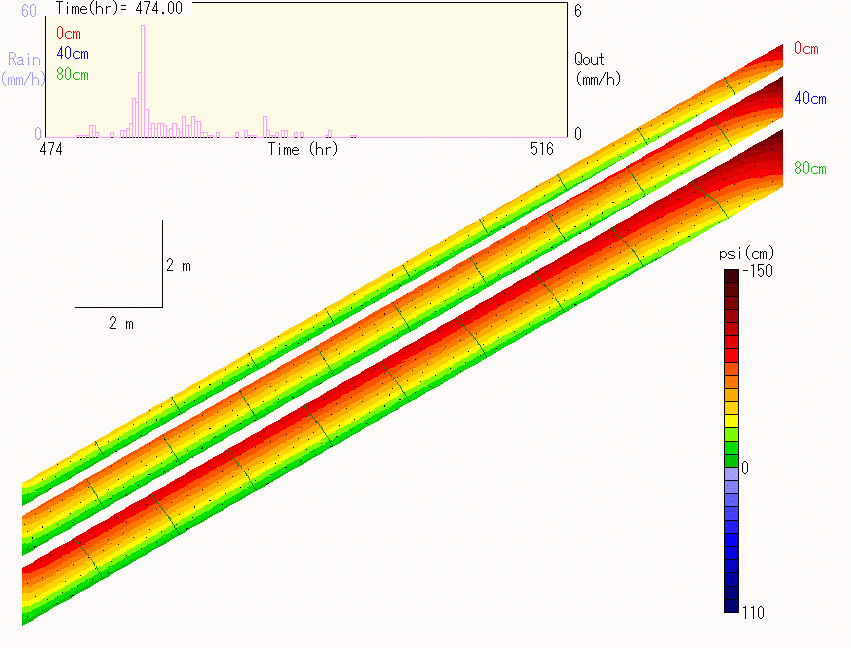
「40 cmの厚さを持つ下層土の上に森林土壌が発達した」状況を想定した数値シミュレーション。森林土壌の厚さを0cm(森林土壌なし),40cm,80cmと変化させた場合の,流出波形(左上図)と斜面土層内の水圧分布(中央図)を計算。
0cm(森林土壌なし)の場合,下層土内の地下水位が大きく上昇して表面流を発生させ,流量ピークが極めて大きくなります。80cmの場合は,森林土壌が雨水を一時的に蓄え緩やかな波形に変換してから下層に供給するため,下層土内の地下水位はあまり上昇せず,洪水流量が抑制されます。